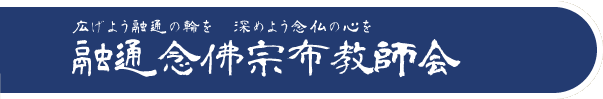この時期寒さが厳しくなってくると思い出すことがあります。それは総本山大念佛寺で受けた水行のことです。
三年に一度、12月下旬に執り行われる修行において本堂へ上がる前に水行にてお経を唱え身も心も清め本堂にてお勤めをするのです。
冷たい水を頭から受けるこの水行とは身体を鍛えるための行だと思われがちなのですが本当の目的は身体ではなく心なのです。
水行は自らの心を正しく見つめる行です。
お水は、文句もいわず選り好みもしません。
暑い日には恵みとなり、寒い日には厳しいものとなりますがお水は何も変わっておらず、変わっていくのは受ける私たちの心の在り方ではないでしょうか。
われわれの心には「冷たい」「つらい」などといった思いがついつい芽生えてしまいます。
そういった愚かさなどに気づかさせてもらえるのもこの水行ではないでしょうか。
私たちは日々、人間関係や病気、老いなどといった思いどおりにならない事ばかりで、それは水が流れて行くかのように起きていきます。
そんな時にこの水行を思いだし、南無阿弥陀仏とお念仏をお唱えしたいものです。
ぜひ皆さんもこの水行を見るご縁がございましたら、何かと忙しく日々の生活を送っているかと思いますが、少し立ち止まっていただき合唱の姿でお念仏を唱え共々に身も心も清めていただくよい機会になるかと思います。(竣)
(撮影:脇坂実希)