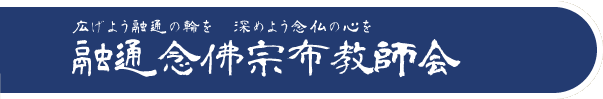6月に入ると大きな神社やお寺の境内に茅(ちがや)やスゲ、薄(すすき)などで拵えた大きな輪が立てられます。
茅の輪と呼ばれるこの輪を潜り抜けることで体に溜まった穢れを落とすことが出来ると言われてきました。
一年十二か月のちょうど半分になる6月。この6月の終わりには「夏越の祓い」という神事が行われ、この半年間に溜まった穢れを祓い、新たに残りの半年をスタートさせるのです。
この時に食べるのが「水無月」という和菓子、外郎(ういろう)の仲間で、三角形をしており、二層に分かれています。上には小豆の赤、これには悪魔祓いの意味があり、下は氷を表す白い外郎。三角形に尖らせるのは氷の角をイメージしたとも、刃物の切っ先を表したとも言われています。
一年の半分を過ぎたところで溜まった穢れと魔を払うためのお菓子という事なのですね。
さて、「茅の輪」にお話を戻します。
その昔、蘇民将来という貧しい生活をしながらも心の優しい人がいました。素戔嗚尊(すさのおのみこと)という神様が姿を変えて一夜の宿を求めた時、貧しい中にも快く持て成したのでした。
そのことに大変感心した素戔嗚尊は、去り際にこの様に言い残しました。
「これから疫病が流行ることになる。しかし、茅の輪を作って腰に下げておけば、その人は疫病にかかることはない。」
その言葉を信じた蘇民将来は言われたとおりにすることで、無事に疫病から逃れることがという事。
昔は腰に下げる程度の大きさだったものが、今では潜り抜けられるほどの大きさとなり、無病息災を祈って「茅の輪くぐり」が行われるようになったのです。そして今でも玄関の上に「蘇民将来之子孫也」と書かれたお札を貼ってある家を見かけることがあります。
これもまた茅の輪くぐりと同じく、疫病に罹らないために素戔嗚尊にお願いをしているのです。
そう考えると日本人は神仏を恐れ、敬い、そして救いを求めてきたのですね。 (善)
(撮影地:村屋坐彌冨都比賣神社 , 撮影:脇坂実希)