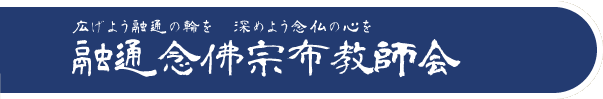梅雨の季節になりました。
梅雨とは元々、雨でじめじめすると黴が生えやすい事から、黴をもたらす雨と書いて黴雨(ばいう)と言われておりました。しかし余りにも言葉が悪いので、発音が同じ梅の字を当てて梅雨(ばいう)と書き、梅の実が熟す頃に降る雨という意味になったと言われております。
近年の駆け足気味の気候を考慮すると正に旧暦の五月雨と言った所でしょうか。
この季節になりますと古来より晴天を祈願し、窓辺や軒下に「てるてる坊主」が吊るされます。
元々「てるてる坊主」は中国から伝わってきたとされています。
昔、中国のある村に掃晴娘と言う娘がおりました。
ある年の6月、村に大雨が降り大変な水害が起きました。
村の人々はこぞって雨が止むようにと雨の神である龍神に祈願し、掃晴娘も村人と共に祈りを捧げました。
すると天から掃晴娘が龍神の妃となるなら雨を止ませるという声が響き渡りました。
村の人々を救うと誓った掃晴娘が頷き、これに同意すると雨は止み、その瞬間に一陣の風が吹いて掃晴娘の姿は消え、引き換えに空は晴れ渡りました。
以来、村の人々は雨が続くと、雲を掃き晴天を齎した掃晴娘を偲んで切り紙で作られた人形を門に掛けるようになりました。
この伝説が日本に伝来し、江戸時代頃から風習として浸透していきその過程で作られていったのが「てるてる坊主」とされています。
嬉遊笑覧という江戸時代の風習を書いた随筆の中に「てるてる法師月に目が明」とありますように、白い紙や布で作り、願いが叶えば目(顔)を描くのが本来の習わしです。
逆様に吊りしたり、白と逆の色で作れば雨が降るともされています。
小さな子供さんでも晴れを願い気軽に作る「てるてる坊主」ですが、その心は実は深いものであります。
人間の力が及ばない自然への感謝、そして手を合わせ心の底から祈り信じる心。
古来より大切にされてきた心です。
今の時代にも脈々と伝わり育まれてきたその心をこの梅雨の季節、「てるてる坊主」に手を合わせ、祈りながら見つめ直してみては如何でしょうか。(哲)